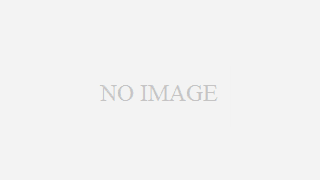 ガン
ガン ごぼうのようなアクの強い野菜がなぜガンに効くのか?
根菜類には、ごぼうをはじめ、きざんで空気にさらすと褐色に変化してしまうものが多くあります。これはタンニン系物質が空気に触れて酸化するためです。ごぼうの場合は、ポリフェノールという無色の物質が酸素によって酸化し、褐色に変色します。一般に、アク...
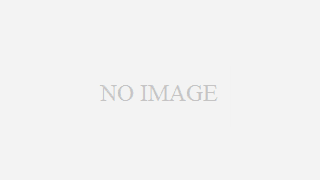 ガン
ガン 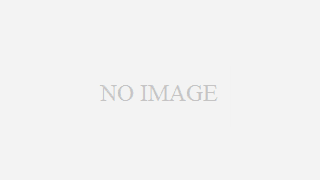 ガン
ガン 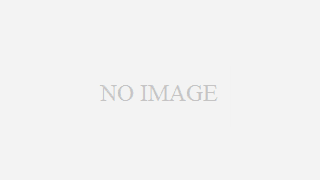 ガン
ガン