 食
食 米 危険 私達の主食にも添加物が使われている事実
米 危険 私達の主食にも添加物が使われている事実があります。pH調整剤が使われています。pH調整剤の危険性について紹介します。米 危険食品業界には30年ほど前まで、国民の健康を考え、「毎日食べる主食のコメに食品添加物は使わない」という不文律...
 食
食 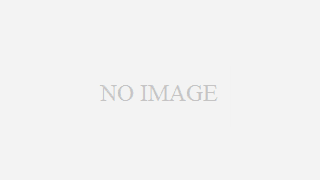 食
食 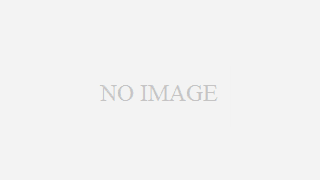 食
食